失敗しない経営計画の立て方~これだけは避けたい5つのNG
この記事の目次
NGその1:本当はいらないと思っているのに計画を立てる

計画なしでうまくいっているなら、とりあえずOK
これからあなたは自宅から自分の会社に向かうとします。
いつものルートですから、乗換案内やカーナビは不要ですね。
わざわざ検索しなくても、電車なら、どこでどう乗り換えて、何分かかるか、知っています。
クルマの場合も、どの道を通って行けばスムーズか、わかっています。
それと同じで、いつもと同じようにがんばって、毎年つつがなく決算を行い、次の期を迎えることができているのなら、何も無理して経営計画を立てる必要はありません。
うまくいっている限りは、計画はいらない
そもそも、たいていのことは、これといった計画なしで実行されています。
世の中、そんなに計画ばかりだったら窮屈すぎます。
ただ、まったく闇雲に行き当たりばったりなのかといえば、そうではありません。
あらためて計画を立てなくても、経験則や習慣化により、自然と身についたやり方でこなしているのです。
それでうまくいっている限りは、わざわざ計画を立てる労力をかけるくらいなら、行動に充てた方が効果的です。
でも、「今年こそ、今期こそ、経営計画を立てて、きっちりマネジメントするぞ!」と気合を入れて、挫折した経験をお持ちの方も少なくないのでは? 意気込みとは裏腹に、計画を立てること自体に失敗して、落ち込んでやる気をなくしてしまったら元も子もありません。
ただし、うまくいかなくなってからでは遅い
「なんだ、経営計画なんかなくてもいいんだ」と思って、ほっとしたかもしれません。
しかし、売上が下がった、社員がどんどんやめていく、仕入れ価格が高騰した、等々の理由で、今まで通りにはいかなくなるのが経営の常です。
それが一時的なものであれば、「いつものようにがんばればいい」のかもしれませんが、それが一時的なものではなく、いつものがんばりでは効果がないとなると、大変です。
計画なしでうまくいっていた、という場合、「なぜうまくいっているのか?」の要因分析ができておらず、再現性に欠ける場合がほとんどです。
この場合、「なぜうまくいかなくなったのか?」の要因分析も的確にできませんから、その苦境から抜け出すのに何が効果的かもわかりません。
そうこうしているうちに、業績も資金繰りも急速に悪化し始めます。
筆者自身も、この急速な下り坂を身をもって体験しました。そうなってから考え始めても、状況が悪化するスピードの方が速いのです。時間をかけて積み上げたものが、あっという間に目に見えて減っていくのは恐怖そのものでした。
計画が必要なのは将来を見越したチャレンジをするとき
振り返ってみると、調子がいいときに、調子がいいことに安住し、「次のビジョン」をまったく考えていなかったのが根本原因でした。
なので、満足した瞬間が業績のピークとなり、ピークである以上は、そこから下がるしかなくなってしまったのです。
うまくいっている間に、もっとうまくいくためにはどうしたらいいかを考えておくこと。これが筆者の得た教訓です。
それはつまり、現状を超えていくチャレンジをすることです。もし自分のいる業界や地域経済が下り坂基調なら、その中で現状を維持するだけでもチャレンジングなことです。
チャレンジとは、「今できないことをやろうとすること」です。おのずと、高い目標を立てて、その達成を目指すことになりますね。
そういうときにこそ、計画が必要です。別の言い方をすると、明確な目標を持たない限り計画は必要ないし、作ることもできません。
目標達成のプロセスを明確化するのが計画なのです。
経営計画は旅行計画のようなもの、最初に決めるのは目的地!
あなたがいつものルートでしか移動しないなら、乗換案内もカーナビも必要ありません。
しかし、今日行くのが初めての場所なら、目的地の正確な住所を確認した上で、乗換案内やカーナビを使って、あらかじめルートと所要時間、費用を調べるはずです。
そして、このルートで行こう、と決めたら、それが計画です。 ただ、どんなにすぐれた乗換案内やカーナビにも、できないことが1つだけあります。
それは、あなたに代わって、あなたの目的地を設定することです。
ですから、経営計画は、旅行計画に似ています。
流浪の旅に出るのなら別ですが、そうでない限りは、旅行に行くときに最初に決めるのは目的地です。
旅行代理店のカウンターに行って、どこに行ったらいいかの相談をして、オススメのパンフレットをもらうことはできますが、最後に決めるのは自分ですね。
あなた自身、そしてあなたの会社の目的地はどこなのか?それを決めるのが経営者の仕事であり、決めた以上は、確実に到達できるように準備する。それが経営計画です。
NGその2:現状分析から始める

現状分析は永遠にできる、ただし結論は出ない
筆者はシンクタンクという業界で12年間、働いていました。
受託業務で、調査報告書を納品するのが仕事でした。
報告書の第1章は、もれなく「現状と動向」です。様々な統計データや書籍、雑誌記事などを調べて、「今、こうなっている」、「傾向からすると、この先こうなる」、「識者はこう言っている」等々の材料を集めて、表やグラフに加工するのです。
ところが、クライアントはなかなかOKと言ってくれません。
あるデータを出せば、もっと別のデータはないか。ある分析をすれば、別の視点はないか。日本の例を出せば、海外の例はないか。
注者のいうことですから、「ハイ、わかりました」と言って、せっせと調べては資料をつくるのですが、これが延々と続くと、さすがにしんどくなってきます。 膨大なデータ集は作れますが、何一つ結論が出ないのです。
で、そんなことをやっている間に、新しいデータが公表されて「最新年次のデータに更新してくれ」、更新してみたら前年までと傾向が違っていて「それはどうしてだ、別のデータと照らし合わせて分析してくれ」、・・・。
役に立つ情報は山ほどあるが、役に立てられるほど消化できない
経営計画も同じです。SWOT分析とか3C分析とか、いろいろな手法があり、データもいくらでもあります。
インターネットで検索すれば、知りたいことについて、何十件、何百件とヒットします。
しかし、データは常に過去のもの。市場もお客様も、取引先も競合も、社員も自分自身も、時々刻々と変化し続けています。その現状に対する肌感覚と切り離されたところでいくらデータいじりをしても、結局「なんかチョット違うんだよね」です。
データを見てその判断がつくのであれば、だったら、その判断基準は何なのかを突き詰めた方が有益だし、話が早いですね。
インターネット検索で出てきた意見や考えは千差万別で、相互に食い違いもあれば、真っ向から対立するものだってあります。
その中から、どれを参考にしたらよいのか、どうやって決めたらよいのでしょう? 他人の意見は他人の意見。
自分自身、自社がどっちを向いているか、向きたいかを自己認識できていなければ、誰の意見も参考にできません。
経営は問題点だらけが当たり前、探し始めたらキリがない
完璧な会社は世の中に存在しません。
ですから、あなたの会社の問題点を見つけようと思えば、いくらでも出てきます。
ただし。5個、10個、30個、100個、、、たくさん問題点が出てきたら、「俺たち、すごいな」とモチベーションは上がるかというと、そんなはずはありません。
むしろ、「俺たち、こんなにダメなのか」と落ち込み凹むのは目に見えていますね。
また、仮に、その問題点を全部つぶせたとします(実際にはできませんが)。
その頃には、また新たに別の問題点がたくさん浮上してきているのです。 イタチごっご、あるいは、もぐらたたきゲームからいつまでも抜け出せません。
そもそも、ネガティブ探しのマインド自体が、社長と社員の力をそいでしまいます。やるならポジティブ探しです。
本当に分析すべき現状は、限られている
実は、経営計画の前段でやるべき現状分析とは、「目的地に到達するために必要なことは何か」を明確化するためのものです。
それを解決したところで、目的地の到達に関係しないような問題点は、優先順位は低いはずです。
そんなことばかりにかまけて、目的地に到達できなくなるような問題点に手をつけないでいたら、どうなるでしょうか?
海外旅行に出発する当日、空港のチェックインカウンターまで行って、「あ、パスポートの期限が昨日で切れていた」なんてことにはなりたくないですよね。
これは、経営にたとえれば、新規事業に必要な許認可が、事業開始予定日までにとれていないようなものです。
設備、人員、商品、広告宣伝、見込客、等々ほかのすべてが準備万端そろっていても、そもそも出発できません。
出発できない以上、目的地に到達できる可能性はゼロになってしまいます。
目的地に到達するのに足りないことにだけフォーカスする!
「猫まっしぐら」というCMがありましたが、経営計画における現状分析は、「目的地にまっしぐら」で考えて、それを邪魔する社内外の要因は何かを特定すればよいのです。
これは、その要因を取り除けば、すなわち目的地に行けるわけですから、ポジティブな行動です。
全方位でネガティブ探しをするのではなく、特定方位に絞ってポジティブ探しをするわけです。
すると、見つかった問題点に対する姿勢も、「困ったな」というネガティブモードではなくて、「どうやって解決してやろうか」というポジティブモードになります。
NGその3:正確さや綿密さにこだわりすぎる
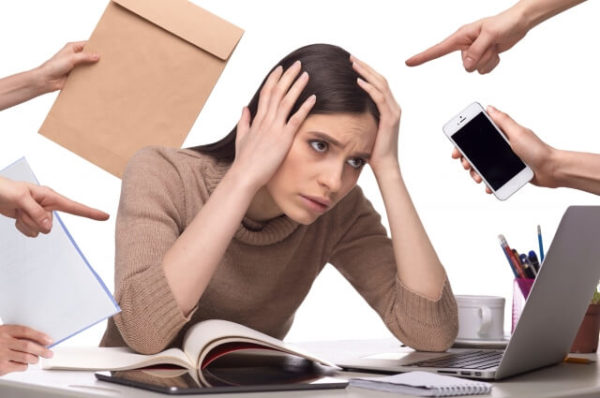
たいていのことは、「やってみなけりゃわからない」
人生同様、経営も、あらかじめ立てた見通し通りに行くことはまずありません。
また、あらかじめ立てた見通しがベストであるとも限りません。
たいていのことは、「やってみなけりゃわからない」のはそのとおりです。ただ、だからといって、何も準備せず、無為無策でこの状況に向き合うわけにもいきません。
これまで何十人、何百人という経営者の方と、かかわり・内容の粗密の差はあれ経営相談を受けた経験から、人は大きく2つのタイプに分かれるようだと考えています。
1つめは、「行動するのが先で、考えるのは後」。思いついた瞬間に、もう動き始めているようなタイプですね。
もう1つは、「考えるのが先で、行動するのは後」。いろいろ思いついたことの中から、よく吟味して選び抜いた行動を実行に移すようなタイプ。
あなたは、どちらでしょうか? ちなみに筆者は、通常はどちらかというと後者ですが、実は人生の大きな決断は、前者のタイプです(それを座右の銘っぽく表現したのが、「感動で決断、論理で行動」です)。
一概にどちらが良いとか悪いとかいうことはないのですが、自分がどちらのタイプかを認識しておくことは有益です。
小さく試してみれば、たいていのことはわかる
「行動するのが先で、考えるのは後」タイプの方は、行動を止められるのが嫌いです。
ですから、「行動をする前に考えろ」とは言いません。
ただ、いきなり大バクチを打つようなことは避けた方がいいでしょう。
小さく試してみて、いわゆる「感触がつかめた」段階で、一度立ち止まって考えてみることをお勧めしています。
たとえば、テレビでは「クイズ100人に聞きました」に始まり、最近では、30人くらいの街頭インタビュー結果、中にはたった10人や5人のモニタリング結果にもとづいて、「世の中こうらしい」と伝える情報番組がたくさんあります。
統計的にはサンプル数が少なすぎて、何ともいえないわけですが、ビジネス上は、このくらいの数を当たれば、大はずれしない情報は手に入ります。
お客さん30人に聞いて、20人が同じ意見なら、それを前提に次の手を考えた方がよさそうですよね。
ゴルフに例えるならば、打つ前に、打つ方向は見極めておきましょうね、といった感じです。
どんなに細かく決めても、変更は必ず起きる
「考えるのが先で、行動するのは後」タイプの方は、いいからやってみなよと、考える時間なしに何かを強制されるのが嫌いです。
ですから、考えてもいいけど、「考える時間を決めて、その時間内に必ず答えを出すこと」をお勧めしています。
未来のことは、「予定」はできますが、「決定」はできません。 パッケージ旅行のように、ときには分刻みのスケジュールが組まれていますが、実際、1分1秒違わずその通りに進行することは、まずありません。
しかし、終わってみれば、回るところは回り、終わる時間には終わるように収まります。
行動することで、予定が決定に置き換えられていきます。予定通りなら予定通りに、そうでないならそうでないなりに、次の行動を決めていくのです。
ゴルフに例えるならば、素振りはほどほどにして、ぼちぼち打ってみましょうよ、球の行く先を見て、次考えましょう、といった感じです。
予算は、まずは概算で立てる
「行動するのが先で、考えるのは後」、「考えるのが先で、行動するのは後」、どちらのタイプにしても、経営計画に不向きということはありません。
ただ、自分のタイプに合った計画の立て方、進捗管理の仕方を知っておいた方がストレスがたまりません。
ところで、このタイプは、お金の面でも対照的になりがちです。
「行動するのが先で、考えるのは後」タイプの方は、いいと思ったら、まさに後先考えずに、バーンと大きなお金を使いたくなってしまいがちです。
積極果敢といえば積極果敢ですが、たいていの場合は無謀な浪費となります。
「考えるのが先で、行動するのは後」タイプの方は、石橋をたたいて渡る、さらには、石橋をたたいた上に渡らないこともザラにありますから、投資のタイミングを失いがちです。
慎重に慎重を重ねた上に、機会損失するのはもったいない話です。
そこで重要なのが、「いくらまでなら今、使えるか、使っていいか」を知っておくことです。
バーンといきたくなったときに、その金額と比べることができます。やめようかどうしようかと悩んでいるときに、その金額と比べることができます。
まずは、顧問の公認会計士または税理士の先生に聞いてみるとよいでしょう。
※「いくらまでなら今、使えるか、使っていいか」を自分で知るための方法の詳細は、別稿で解説したいと思います。
お金も行動も、仮説でめどをつければOK!
最初から正確な情報にもとづいて綿密な計画を立てようとすると、いつまでたっても完成しません。
未完の計画というのは、計画がないのと同じなので、だったら、ないなりにやってしまえということになります。
完成度は低く粗っぽくても、一度完成させてしまえば、やりながら精度を上げ、きめ細かさを増していくことができます。
目測・目分量しかないなら、それにもとづいて仮説を立てて、検証するところから始めればよいのです。
シンクタンクで仕事をしていたときも、「ここは、エイヤーで決めるしかないな」ということが多々ありました。
「エイヤー」というのは、情報集めも根拠づくりも、もうこの辺でやめにして、「決断しましょうや」ということです。
NGその4:カッコイイ言葉で書こうとする

どうせ書ききれないので、時間の無駄
経営計画を作るぞ、となると、それは社員に読ませたり、金融機関に提出したり、人の目にさらされることになります。
そうすると、「こんなこと書いて恥ずかしくないかな」「立派だと思われたいな」という気持ちが働いて、急に有名なビジネス書を読んで、「いいとこどり」しよう、そこまでいかなくても「言葉だけ拝借」しよう、という誘惑にかられるかもしれません。
ところが、しょせん付け焼刃ですから、よそから借りてきたところだけ、どうしても浮いてしまうのです。
筆者は、大学講師としてレポートの採点、資格制度の試験官として論文課題の採点、審査員として補助金申請書の審査などを経験していますが、気取って書いた言葉、丸パクリの文章は、読む側からするとバレバレなんですね。
無理をすることはないのです。
社長の口から出たことのない言葉に力はない
筆者は、エコアクション21という環境マネジメント認証制度の審査人業務も行っていますが、審査では必ず、受審企業の経営者にインタビューをする規定になっています。
せいぜい30分ほどの時間ですが、こちらは質問をする側なので、大半は経営者が話す時間になります。
審査業務なので、一定の基準に照らして評価する材料を得ることが目的です。
すると、社長名で制定されている「環境方針」に書き連ねている言葉が、一つも出てこない、ということがよくあります。
そこで、「社長、すいませんが、この環境方針、今、読み上げていただけませんか?」とお願いすることがありますが、案の定、読めないんですね。
余談ですが、マネジメントシステム規格というのは、経営者の定めた方針がすべての出発点となるように構成されているので、とても重要な文書です。
だから、受付には環境方針が印刷された紙が置かれていて、壁には額縁に入って掲示されているのです。
社員は日々、それが目に入ります。 しかし、日常、そこに書かれている言葉は社長の口から一言も出てこないし、読めと言われても読み上げられないのです。
もし、経営計画書がそうだったら?考えるだけでも悲惨ですね。
書く前に、ためしにしゃべってみる
文章を書くのが苦手な人はたくさんいます。10人中、8人、9人はそうだといっても過言ではありません。
しゃべるのが苦手という人もたくさんいます。
こちらも、10人中、8人、9人はそうだといっても過言ではありません。
しかし、しゃべる方は、本人は苦手と言っていても、いい聞き役がいれば、10人中、8人、9人はうまくしゃべれるのです。
経営相談でも審査での代表者インタビューでも、「あれ、今日は調子がいいぞ」、ということで、この人こんなに話す人なのかと思うくらい、饒舌に話していただけることが多々あります。
しゃべったことは、一度言葉になっているから必ず書ける
そこで一段落ついたら、こんな会話をします。
「社長、書くのもしゃべるのも苦手とおっしゃいましたよね」
「うん、言った」
「でも、今、ご自身のお考えを、ご自身の言葉でずいぶん話していただけましたよね」
「そういえば、そうだな」
「しゃべれたということは、言葉になったということです。一度、言葉になったから、書けますよ」
「え、でも、こんな与太話みたいなこと書いてもしょうがないだろ」
「そうですか、でも、社員は今みたいな話、聞きたいと思っていますよ」
「そうかな、でも、何をどう話したかな、覚えてないよ」
書くのが苦手という意識がすぐには払しょくできず、書くのは億劫だなという思いもあるので、「覚えてないよ」とおっしゃいますが、そんなことは絶対にありません。
自分が言ったことを、言ったそばから忘れるようだったら、経営者がつとまるはずがありません。
本当にそうだったら、そんな相手と、うかうか取引できないですよね。
一度自分の口で話したことは、脳裏と心に、確実に刻み込まれてます。
自分の言葉でアツく語れるのがいちばんカッコイイ!
経営計画書というと、文書・書類ですから、それだけで独り歩きしそうです。
しかし、社内に向かっては、社長が社員に会社の将来を話す際の根本シナリオになります。
いつでも、同じように、ブレずに話すための台本といってもいいでしょう。
社外に向かっては、融資獲得のために金融機関、補助金申請のために行政機関に提出しますが、たいていの場合、「面接」「面談」がついてきます。
この面接・面談で何をやるのかといえば、社長の口から出てくる言葉と、経営計画書に書いてあることに相違がないか、齟齬がないか、要するに、たしかに社長が自分で考えたことが書かれているのかどうかの確認です。
ここでも、シナリオであり台本です。
他人のカッコいいセリフを、舌をかんだり、読み間違えたりしながら覚束なげに読み上げるより、自分のセリフを、自分でアツく語れた方が、よほどカッコいいですよね。
NGその5:時間をかけすぎる

いちばん大事な経営資源は時間
社長は会社に1人しかいない、最重要の経営資源です。
人が使える時間は、社長であっても社長でなくても、平等に1日24時間しかありません。
力を注ぎ、細かいところまで正確さにこだわり、カッコイイ言葉探しに明け暮れ、挙句、放り投げてしまったらすべて無駄です。
投入した時間に社長の時間単価をかけてみてください。これほどもったいないことはありません。
とくに目指すべき目的地が見つからなければ、目の前のことに集中した方がよい
「何にチャレンジしたらいいかわからない」
「どこを目指したらいいかわからない」
「ビジョンを持たなければいけないのでしょうか?」
「目標って立てなければいけないのでしょうか?」
経営相談では、こうした声・問いかけにも少なからず接します。
そういうときは、こう尋ね返します。
「何にチャレンジするか、どこを目指すかがわからないことで、何か問題がありますか?」
「持たなければいけない、立てなければいけないと思う時点で、ビジョンや目標の必要性が薄いということではありませんか?」
答えが、「問題はない、必要性がない」なら、当面は、それに時間をかけるよりは、お客様により満足していただくことや、品質を向上することや、従業員に変化がないか気に掛けること等々、目の前のことに集中した方がよいでしょう。
いや、「それでは問題がある、必要はある」、ということであれば、正面から取り組んだらよいのです。
ほかの重要事をおろそかにするようでは本末転倒
経営者ならずとも、効果的な時間管理は永遠の課題です。そのために、緊急度と重要度で優先順位をつけて時間配分をするという考え方があります。
今期の売上をどうするか、来月の集客をどうするか、今週の支払いをどうするか、今日のシフトをどうするか、等々、緊急性が高く重要度も高い課題はたくさんあります。
これを放置しておいたら、極端な話、経営が立ち行かなくなり、計画どころの話ではなくなってしまいます。
一方、経営計画は未来に関することです。ですから、緊急性はあまり高くないですが、重要度が高いテーマです。
いずれそのうちと先延ばしにしている間に、タイミングを逸してしまいがち。取り組む期間とかけてよい時間数の上限を決めておくとよいですね。
市場もお客様もどんどん変わるので、スピードが大事
今の時代、市場環境もお客様のニーズや好みも、どんどん移り変わっていきます。
「よし、やらなきゃ」と思った瞬間から、自社の置かれた状況は変化し続けていますし、自分自身の関心も変わります。
鉄は熱いうちに打てといいますが、打つだけでは不十分で、刀剣なり、包丁なり、形をなすところまで一気に仕上げてしまう必要があります。
そうでなければ、何にも使えない、冷えた鉄の塊が残るだけです。
経営計画も同じです。
単年度計画を立てるのに半年もかけていたら、できたときには、もう半分終わっています。
第4四半期にもなれば、だいたい着地予想がつきますから、今期もあと残り2-3ヶ月というタイミングで着手して、決算月が終わるまでには完成させたいところです。
期日に間に合う60点でスタート!
シンクタンクでの新人時代、締め切りに追われる日々の中で教わった教訓があります。
「期日に間に合わない100点は0点」
「それより、期日に間に合う60点の方が大事」
これは、20数年たった今でも、実務的に役に立つ指針になっています。
実は、いろいろな試験の合格点、評価の及第点は、多くの場合、60点のラインに設定されています。
100点で合格しても60点で合格しても同じです。
60点で足りない部分は、これから整え、磨き上げる余地があると思って、欲張らずに、ひとまず形に仕上げてしまいましょう。 どんな「形」にしたらよいのか?それは別稿をお楽しみに!
まとめ
経営計画だからと肩肘はらずに、自分の思いを言葉にしてみましょう! 信頼できる話し相手を見つけて話すのが一番の早道 文字や数字や図解で計画書にまとめるのは、その後で!
もし、この記事が参考になりましたら、記事作成の励みになりますのでいいねをお願いします。

